「老後」という言葉を聞くと、どんなことが思い浮かびますか?
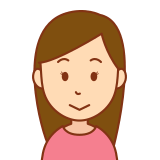
老後ってまだまだ遠いような。。。
でも目の前のような。。。
内閣府の2022年10月実施の「国民生活に関する世論調査」では、63.5%が「老後の生活設計について」悩みや不安があると回答しました。
かなりの割合ですね。
「40代から始める片付け|リバウンドなし&不用品売却ガイド」のりょうこです。
先日、ご近所づきあいのある62歳のAさんから興味深い話を聞きました。
Aさんは最近、腰を痛めて入院することになり、40年分の思い出の品々が詰まった家の整理に頭を抱えているそうです。

若いときから少しずつ整理していれば、こんなに大変な思いをしなくて済んだのに…
このAさんの言葉が、私にとって大きな気づきとなりました。
私自身、40代になって体力の衰えを感じ始め、将来への漠然とした不安を抱えるようになっていました。
そんなとき、「もしかして、日々の片付けが老後対策になるんじゃないか?」と考えるようになったのです。
なぜ40代からの断捨離が老後対策になるのか? 3つの重要な理由
近所に住む70代の方々との立ち話や、ネット上の体験談を見ていくうちに、40代からの片付け・断捨離が将来の暮らしを大きく左右することが分かってきました。
その理由をご紹介します。
理由1:身体的な負担の軽減
筑波大学大学院の久野譜也さんによると、筋力は40代から年間1%ずつ低下するみたいです。
60代になると、40代と比べて約2割も筋肉が減っているという状態になるそうですよ。
( https://www.asahi.com/relife/article/11638180 )
先日、整理収納セミナーに参加した際、講師の方が興味深い話をしてくださいました。
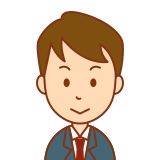
50代で断捨離を始めた方が、『若いうちに始めておいて本当に良かった』とおっしゃっていました。
70代になった今でも、すべての収納物を自分で取り出せる環境が保てているそうです。
やっぱり体力のある間に、快適に暮らせる環境を作っておくことはとても大事みたいです。
理由2:心理的な安心感の醸成
一般的に、整理整頓された生活環境はストレスの軽減や気分の安定につながります。
そこから、高齢者のメンタルヘルスにも良い影響を与える可能性が語られています。

メンタルが健康であれば、老後も幸せに楽しく過ごせそうですね!
理由3:時間とエネルギーの有効活用
年齢を重ねて筋力・体力がなくなってくると、同じ家事をするにも時間がかかるようになります。
でも、片付けをして物が少ない状態であれば、掃除の時間が短くなります。
調理器具も必要なものにしぼっておけば、迷う時間が減って料理時間の短縮につながります。
その分、時間的余裕ができるといういい効果もあるようですよ。
SNSで見つけた65歳の方の投稿が印象的でした。
今では掃除時間が3分の1になり、その分趣味の絵画教室に通える余裕ができました

片付けや掃除が大好きであればいいんですが、したいことがあるなら、若いうちからある程度整理していたほうが、老後に時間的余裕がありそうです。
【実践版】40代から始める老後を見据えた断捨離ステップ
インターネットで「40代 断捨離」に関する検索数は、どんどん増えてきているみたいです。
それだけ、同世代の多くが関心を持っているテーマと言えます。
ステップ1:未来の自分を想像する意識的な第一歩

スクールバス空間設計が2024年に実施した調査によると。。。
60歳以上の一戸建てに住む人のうち、約81.2%が「今後も現在の家に住み続ける予定」と答えています。
一方で、80代の人に聞いた話がこちら。
「若いときに『将来』を考えて家を建てたつもりが、想像以上に階段の上り下りが大変になってね。」
やっぱり若いときには想像ができない変化が、実際には起きるみたいです。
そこで、もしあなたが今の自宅に住み続けるつもりであれば、以下のようなポイントを明らかにしてみましょう。
実践ポイント
- 10年後、20年後の暮らしをノートに書き出す
- 家族と将来の住まい方について話し合う
- 現在の家の不便な点をチェックリスト化する
やっぱり紙に書いたり、マインドマップを作ったりすると明確になって分かりやすいですよね。
今まで気づかなかった意外なポイントが見つかることもあります。
ステップ2:住まいの安全点検とリスク低減アクション

高齢者は自宅内でつまづいたり、転んだりしてケガすることが非常に多いようです。
私の母の友人は、床に散らかっていた雑誌につまづいて転倒。
骨折してしまったそうです。
ひょいひょいと避けられる若い頃と違って、歳を重ねるとちょっとしたことでケガをしてしまう可能性が高まります。
若いときよりも、片付けの重要性は上がると考えて良さそうです。
安全点検リスト
- 廊下や通路に置かれた物の有無
- 照明の明るさチェック
- 床材の状態確認
- 家具の配置の見直し
快適性だけではなく、安全のためにも物はしっかりと片付けたほうが良いですね。
ステップ3:身体的な負担を軽減するための「重い」「大きい」モノの見直し

歳を重ねると、ちょっとした作業でも体を痛める可能性が高まりますね。
さっとできていたことで、体に違和感を感じる。。。
切ないですが、仕方ありません。
先日、SNSで見かけた45歳の方の投稿に、とっても納得しました。
「実家の大掃除を手伝ったとき、母が20年使っている重い食器棚の開け閉めに苦労している姿を見て、自分の家の家具を見直すきっかけになりました。
重いものを軽量なものに換えたり、大きな家具を分割できるタイプに替えたり…。
そのときの投資は決して安くありませんでしたが、『将来の自分への投資』だと思えば納得できました」
親のためが、めぐりめぐって自分のためになるわけです。
具体的な見直しポイント
現段階でも、「重い」「大きすぎる」「多すぎる」と感じる家具や家の中のアイテムはありませんか?
今のうちに見直しておくと、年を取ってからとても楽かもしれませんよ。

私自身は今まで、使い勝手が良く、あまり大きすぎない家具を選んできたつもりです。
ですが、時間経過や生活スタイルの変化で、今後は感じ方が変わるかもしれません。
そのときには躊躇せずに、必要経費と思って買い替えていきたいと考えています。
好みも変わるでしょうし、買い替えのいい機会になると思えば、面倒なことばかりでもなさそうです♪
ステップ4:心理的な負担を軽減する「長年の」「多すぎる」モノの整理
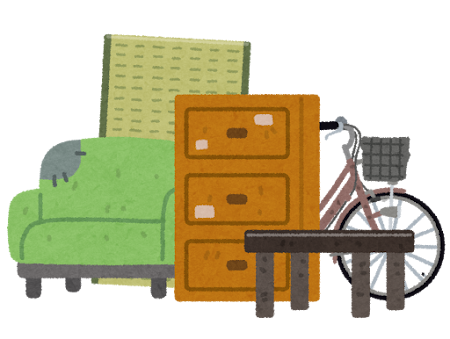
あんしん解体業者認定協会が全国の男女500人を対象に実施した調査では。。。
「物を捨てられない」「あまり捨てられない」と答えた人が合わせて55%もいるそうです。
また、株式会社プラネットが実施した調査によると。。。
年代が上がるにつれて「物を捨てられないから片付かない」と感じる人の割合が増加する傾向があるようです。
遺産整理について、知り合いがこんなことを言っていました。
「両親の遺品整理をした時、段ボール30箱分の思い出の品に圧倒されました。
自分も同じように子供に負担をかけたくないと思い、40代後半から少しずつ整理を始めています」
段ボール30箱って冗談でしょ?と思うんですけど、冷静に考えてみるとこれくらいになってもおかしくない、と感じました。
思い出の品整理のコツ
- 現像された写真は、特に思い出深いものだけを残していく
- 子どもの作品は時期・年齢ごとに厳選
- 手紙やカードも特に大切な人からのもののみ保管
思い出の品は本当に手放しづらいものです。
ですが、実際に開けもしない・見もしない・飾りもしないというケースが非常に多いです。
その状態が思い出の品にとっていい状態なのか。
そんなことも考えていきたいですね。
ステップ5:デジタル化と情報の集約で「管理」を楽にする工夫

株式会社アンビシャスの2025年の調査によると。。。
書類の保管に関して困っていることがある・多少あると答えた人が全国で78.2%いたそうです。
これはすごいですね。
約8割の人が書類保管に困っているそうです。
収納スペースがないとか、要・不要の判断に困るとか、個人情報がある書類の処分に困るとか。
確かに、いろいろと面倒なことが多いですね。
デジタル化すると収納スペース問題は解決できるので、上手に活用していきたいですね。
デジタル化の前に
デジタル化の前に、とにかく数を減らすことが重要になります。
まずは「明らかなゴミ」から処分していきましょう。
期限が切れた保証書、終わった行事の概要や詳細、中学生になった子どもの小学校時代のプリント。。。
明らかなゴミを減らすだけで、かなり量は削減できるのではないでしょうか。

量を減らさないと、デジタル化も大変です!
「老後を楽にする」空間作りの具体策
いくつになっても必ず発生するのが、物の出し入れ。
食器や調理器具、服、趣味のもの。。。
だからこそ、家庭内では物の出し入れの際に、体を痛めることが多いようです。
引き出しを引っ張り出すときに腰を痛めたり、高いところから取り出すときに落としてしまったり。。。
出し入れしやすい収納を作るのは、老後を快適に暮らすためにとても重要なポイントです。
1. ユニバーサルデザインを意識した収納

実際に近所の工務店で聞いた話では、「最近は40代からリフォームを考える方が増えており、その8割が『将来の暮らしやすさ』を重視している」とのことでした。
具体的には収納に大きめの取っ手を付けるとか、引き出しはレール式にしてスムーズに出せるようにするとか。
クローゼットの中に照明を付けるケースも増えてきているようです。
2. 掃除のしやすい住環境づくり
掃除も重労働のひとつです。
なので、掃除をしやすい環境を作るのも大事です。
段差を減らすとか、物は床に置かないようにするとか。
掃除機は各階に用意するとか、お掃除ロボットを使うとか。
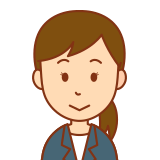
物を減らせれば掃除も楽になって、高額なお掃除ロボットを買う必要もないのでは?
と、私の友人は言っていました。
3. 収納位置の最適化
収納は高さによって、使い勝手が大きく違います。
よく使うものは使いやすい高さや場所に収納する。
高いところの収納は使わなくて良いように物を減らす。
このような工夫で、日々の動きが楽になります。
日々の動きが楽になれば、意図しない事故に遭う確率も減りますね。
40代からの断捨離、よくある困難と解決策
SNSやブログでよく見かける悩みとその解決例をまとめてみました。
日々の片付けに活用できる項目ばかりですから、普段から習慣化するのがおすすめです。
【困難1:時間が取れない】
まとまった時間って取りにくいですよね。
仮にまとまった時間が取れても、すぐに疲れて効率ダウンというケースも。

なので、毎日この時間に15分だけ行う!とスケジュールに組み込んだり、スキマ時間ができたらここを片付ける、と決めておきましょう。
短時間の方が意外と進むんですよね。
【困難2:家族の協力が得られない】
家族の協力が得られないというケースも多いです。
まずは自分のものから始めましょう。
自分のものを楽しく、真剣に片付けしているとその雰囲気が家族に伝わる、ということは本当にあるんですよね。
なんか「自分もしなきゃ」ってあせる、みたいな感じになることも。
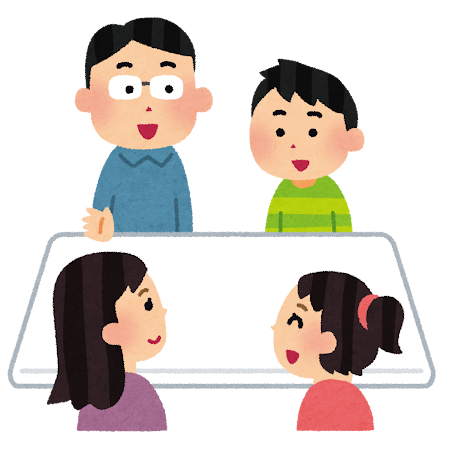
あとは、自分の要望を家族会議で話して、家族に認識してもらうというのも効果的です。
【困難3:捨てられない気持ちが強い】
「捨てられない」というのもよくぶち当たる壁です。
使っていないのに捨てられない、というケースですよね。
その気持ちはとても分かります。
でも、それがその物にとって本当に良いことでしょうか。
私はそんなことを考えるようになってから、かなり手放しやすくなりました。
フリマアプリの普及も手放しやすさを後押ししてくれています。
季節別・40代からの賢い断捨離カレンダー
年間を通じた計画的な取り組みも、片付けを無理なく続けるひとつのポイントです。
季節のイベントは片付けのきっかけに、とっても有効です。
春(3-5月)
- 衣替えのタイミングで衣類や寝具の見直し
- 花粉の季節に合わせて布製品の整理
- 新年度開始に合わせて書類の整理
スペースがとても広がった一方、使ってあげられずに申し訳ないという気持ちになりました。
定期的に片付けられる、いいきっかけになっています。
夏(6-8月)
- 暑い時期を利用して屋内作業
- 大型家具の見直しと移動
- 冷蔵庫・食品庫の整理
だからこそ、部屋の中で大掃除・大片付けをしましたが、クーラーの効いた部屋の中なので、とてもはかどりました♪
冷蔵庫の中に常に余裕を持たせておくことで、見渡しやすく、食品の早期使い切りがしやすいです。
節電にもなるみたいです。
秋(9-11月)
- 防災用品の見直し
- 衣替えのタイミングで衣類や寝具の見直し
- 夏物家電のチェックや使わなかったものの廃棄
ローリングストックや子どもの服なんかをチェックするようにしています。
直前のシーズンに使っていないものは記憶にも新しくて、整理しやすいんです。
冬(12-2月)
- 大掃除に合わせた全体整理
- 年末年始の書類整理
1年分あれば良いものはこの時期に片付けるのがいいですね。
冬はいろいろと多忙なことが多くて、なかなか片付けに向き合う時間が取れないんですよね。
でも、大掃除しているからいいかな、って思ってます。
経済的メリットと環境への配慮
東証マネ部!が2025年2月に発表した調査によると。。。
73.6%の人が「断捨離をして節約効果があった」と答えています。
これはすごい確率ですね。
具体的にはこんな感じです。
- 無駄な衝動買いなどがなくなった
- 同じものを買ってしまうことがなくなった
- 収納グッズを買うことがなくなった
- 長く大事に使うようになって、新しいものを買わなくなった
- 不用品売却で利益が出た
また、地球環境面にも貢献できます。
- 買い物を減らすことでゴミが出ることを防ぎます
- 不用品を誰かが使ってくれることで、リサイクル率が向上します
- 冷蔵庫や部屋を整理することでエネルギー効率が良くなります
老後は自由に使えるお金も減ってきます。
片付けはケガ防止になるだけでなく、お財布にもやさしいんですね。
老後に向けて、ぜひ取り組みたいです!
まとめ:今からできる「賢い老後対策」としての断捨離
「60代になって後悔すること」の上位に「もっと早くから片付けておけば良かった」が入っているそうです。
私自身、少しずつ実践してきた断捨離で実感したことがあります。
- 掃除時間が2割程度短縮
- 必要なものがすぐに見つかる
- 家族との会話が増えた
- 将来への不安が軽減
40代からの断捨離は、決して「もの」を減らすだけの作業ではありません。
それは、より豊かな老後のための具体的な準備であり、現在の暮らしも快適にする賢い投資なのです。
今日からでも明日からでも、あなたの身近なところから、小さなところからでも少しずつ始めてみませんか?
きっと10年後、20年後の自分に感謝される選択になるはずです。
そのときが楽しみですね!


