「捨てたい気持ちはあるけれど、どうしても手が止まってしまう…」
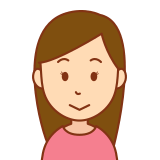
いつか使うかも。もったいない。思い出が。。。
いろんな気持ちがあって、捨てられないの。。。
片付けあるあるですよね。
捨てられないという気持ちは誰しも持っているものですし、必ずぶつかる壁です。
私もかつては、目の前のモノの山を前に途方に暮れ。。。
「いつか使うかも」「まだ使える」という言葉が頭の中でぐるぐると回り、なかなか手放すことができませんでした。

「40代から始める片付け|リバウンドなし&不用品売却ガイド」のりょうこです。
40代で仕事と家事に奮闘する日々の中で、私も長年「捨てられない」という悩みを抱えてきました。
思い出の品、子どもの作品、いつか使うかもしれない日用品…。
それらは大切なものでありながら、気づけば部屋を圧迫し、片付けたい気持ちはあるのにどうにもこうにも進まない。
でも、大丈夫です!
長年の試行錯誤の末に、私でも無理なく、少しずつ片付けを進められる方法を見つけたんです。

それは、特別な才能や根性が必要なものではありません。
考え方と簡単なルールを知るだけで、「捨てられない」あなたも必ず片付けを前に進めることができます。
一歩も二歩も進めることができますよ!
この記事では、かつての私と同じように「捨てられない」と悩むあなたに向けて、少しずつ片付けを進めるための3つの簡単なルール。
そして、それを実践するための具体的なコツをご紹介します。
片付けの最大の敵のひとつ「捨てられない」状態を抜け出していきましょう!
なぜ「捨てられない」のか?その理由を探る
私たちがモノを「捨てられない」と感じる背景には、様々な理由があります。
- もったいない
- まだ使える
- いつか必要になるかもしれない
- 大切な思い出が詰まっている
- 忙しくて判断できない
- 片付けるなら完璧にしたい
理由は1つだけということもありますが、私たちの価値観や記憶、未来への不安などが複雑に絡み合っていることも多いです。
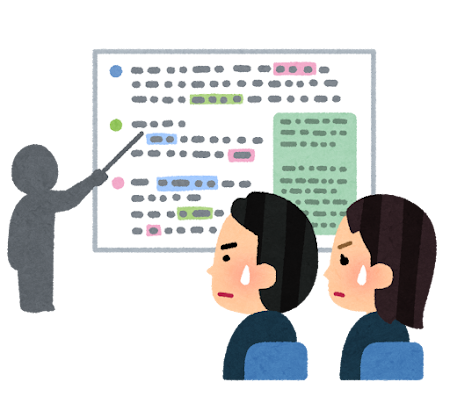
例えば、「もったいない」と感じるとき。
モノそのものの価値だけでなく、わざわざお金を出して買ったことへの意識や、資源を無駄にしたくないという気持ちがあるからでしょう。
両親や祖父母から、「使えるものを捨てるのはもったいない」という教育を受けた影響かもしれません。
「いつか使うかも」という気持ちは、未来への備えであると同時に、決断を先延ばしにしたいという気持ちの表れかもしれません。
そして、「思い出の品」を手放せないのは、モノに宿った記憶や感情までも失ってしまうような気がするからかもしれません。
「忙しすぎる」と判断力が鈍ってしまって手放すかどうかの判断がしにくくなりますし、「完璧主義が強すぎる」と1個手放しても無駄と思うかもしれません。
大切なのは、無理に感情を押し殺して捨てるのではなく、そう感じる理由を理解して素直ににモノと向き合うこと。
捨てられない物と素直に向き合うことで、理由が見えてくるんですよ。

理由が分かれば、手放すための適切な方法が少しずつ見えてきます!
【実践版】「捨てられない」あなたもできる!少しずつ片付けを進める3つの簡単ルールとコツ
それでは、「捨てられない」あなたでも、無理なく片付けを進めるための3つの簡単なルール。
そして具体的なコツをご紹介します。
ルール1:まずは「使っていないモノ」から見直す
「捨てられない」と感じるモノの多くは、私たちの感情と深く結びついているものです。
だからこそ、最初は感情的な結びつきが薄い「今現在使っていないモノ」から見直すのがおすすめです。

具体的な手順
1.クローゼット、引き出し、棚など、家の中の気になる場所で、「過去一年以上使っていないモノ」を探してみましょう。
2.「いつか使うかも」と思って保管しているモノは、本当に「近い将来」使う予定があるか、想像してみましょう。
具体的に思いつかない、使う状況になる確率がとても低いということが分かれば、すっと手放せるかもしれません。
もしくは一旦保留にするのも手です(ルール2参照)。
3.迷ったら、「もし今日、これがなかったら困るか?」と考えてみてください。
困らないようなら、手放す候補になります。
4.「まだ使えるけれど、自分はもう使わない」モノは、リサイクルや譲渡、売却を検討してみましょう。
「捨てられない」あなたへのアドバイス
最初は、明らかに不要なモノ(壊れている、汚れている、サイズが合わないなど)から始めてみましょう。
または小さなモノから始めるのもおすすめです。
価格が安かったモノも手放しやすいです。

明らかに不要なものやサイズが小さいもの、安かったものは、心理的な抵抗が少ないので、まず手放すのにとってもおすすめです!
ルール2:「保留ボックス」を活用して、決断を先延ばしにする
「使っていないけど、今すぐには捨てられない」と感じるモノは、無理に手放す必要はありません。
「保留ボックス」を用意して、一旦そこに入れるというルールを作りましょう。

具体的な手順
1.段ボール箱やプラスチックのコンテナや買い物カゴなど、何でも良いので「保留ボックス」を用意します。
2.「捨てるかどうか迷うけれど、今は決められない」というモノを、この保留ボックスに入れます。
3.保留ボックスには、入れた日付を記録しておきましょう。
A4の紙に書いて貼り付けておくなど、分かりやすく記録しておきましょう。
4.一定期間(例えば3か月後、半年後など)が経ったら、再度保留ボックスの中身を見直します。
入れた日付と一緒に期限を書いておくのがおすすめです。
見直したとき「やっぱり必要なかった」と感じるモノは、心から納得できるので手放しやすくなります。
「捨てられない」あなたへのアドバイス
保留期間をしっかり決めることで、「いつか」が確実な期日に変わります。
締切があると、動きやすくなるのが人間というものです。
見直しの際には、「もし今、これをもらったら自分は使うか?」という視点で考えてみるのもいいですよ。

数か月以上に渡って、なくても生活できたものは、手放してしまっても問題ないケースがほとんどです!
ルール3:「感謝の気持ち」や「循環」を意識する
モノに愛着がありすぎて捨てられない場合は、「感謝の気持ち」を持つことを意識してみましょう。
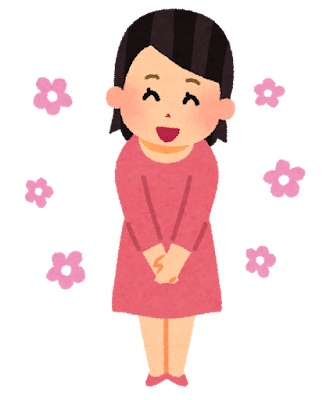
具体的な手順
1.モノに対して、「今までありがとう」という気持ちを心の中で伝えます。
もちろん、声に出してもいいです。
私は小さな声で声をかけることが多いです。
感謝の気持ちを込めて、その物自体を丁寧に拭いたり、包んだりするのも良いでしょう。
その物自体に「新しい人生を歩んでもらう」という気持ちを持つことで、手放しやすくなった人も多いです。
2.まだ使えるモノであれば、リサイクルショップに持ち込んだり、フリマアプリで販売したり。
必要としている人に譲ったりすることも、感謝の気持ちを形にする一つの方法です。
「モノの循環」を意識できれば、手放しやすくなります。
「捨てられない」あなたへのアドバイス
特に思い出の品は、手放す難易度が高いです。
そんなときは無理に手放さない、という選択肢ももちろんありです。
または、写真に撮って記録に残したり、本当に大切なものだけを厳選して保管したりするのも良いでしょう。
子どもの作品なども、全部残すのではなく、特に思い入れのある数点だけを残すということを意識して選択をするのもいいですね。

思い出の品は本当に難易度が高いです。
もっともっと片付け上級者になるまで保留にするのもおすすめです。
片付けがうまくいかない人がやりがちなNGパターン3つ
「よし、片付けよう!」と思って始めたのに、なぜか途中で挫折してしまった。。。
そんな経験はありませんか?
実は、捨てられない人ほどハマりやすい「やってはいけない片付け方」があるんです。
ここでは、よくあるNGパターンを3つ紹介します。
自分に当てはまっていないか、チェックしてみましょう。
NGパターン1:思い出のモノから手をつけてしまう
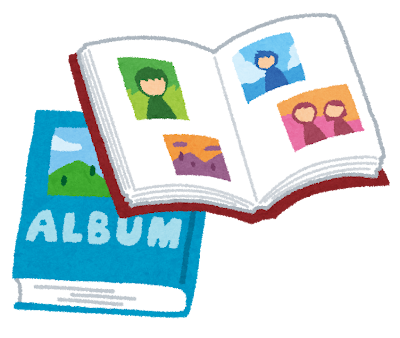
いきなり「アルバム」「子どもの作品」「プレゼント」などに手をつけていませんか?
感情を動かされるもの、一点物などからから始めると、間違いなく手が止まります!
これらは片付けの中でも最高難易度を誇ります。
片付けに慣れてから取り組むのがおすすめです。
まずは「感情が薄いモノ」「今使っていない日用品」など、判断がラクなモノからスタートするのがポイントです。
NGパターン2:「とりあえず全部出す」で疲弊

「全部出してから分類する」と片付け方法はよく聞きますよね。
この方法は確かに正解です。
ですが、片付けが苦手な人にとっては逆効果になることも。
途中で力尽きて、余計に散らかってしまうケースがよくあります。
最初は、一か所・一カテゴリー・10分だけなど、小さく区切る片付けがおすすめです。
NGパターン3:「全部一人でするべき」と思い込む

「片付けは自分の問題だから」と、誰にも相談せず抱え込んでしまう人も多いです。
でも、孤独な片付けはモチベーションが続かない原因にも。
自発的に動いてくれない家族にイライラして、不満をぶつけてしまうケースもあるあるです。
信頼できる家族・友人に相談したり、SNSやブログで成果をシェアするなど、自分だけで抱え込まない工夫をするのがおすすめです。
片付けにも「やらないほうがいいこと」がある
片付けは「やり方」が大事です。
「NG行動をしない」ということも、とても大事です。
上記のNGパターンを避けることで、より自分に合った片付けスタイルが見えてきますよ。
他にもありがちな片付け失敗例はこちらで紹介しています。
ぜひチェックしてみてください!
↓ ↓ ↓

「捨てられない」あなたへのモチベーション維持のコツ
少しずつでも片付けを進めていくためには、モチベーションを維持することが大切です。
具体的なモチベーション維持のポイントをご紹介します!
小さな成功を記録する

片付けた場所、手放せたモノの数を記録することで「片付けはちゃんと進んでいる」という実感を得られます。
目で見て確認する

片付け前後の写真を撮っておくと、変化が分かりやすく、達成感を感じることができます。
誰かと小さな成果を共有する

家族や友人に「今日はこの引き出しを片付けたよ」と報告するだけでも、承認欲求が満たされ、次のステップへのモチベーションになります。
SNSに投稿するのもいいですね。
ご褒美を設定する

目標を達成したら、自分にご褒美を用意するのも良いでしょう。
理想の暮らしを常にイメージする
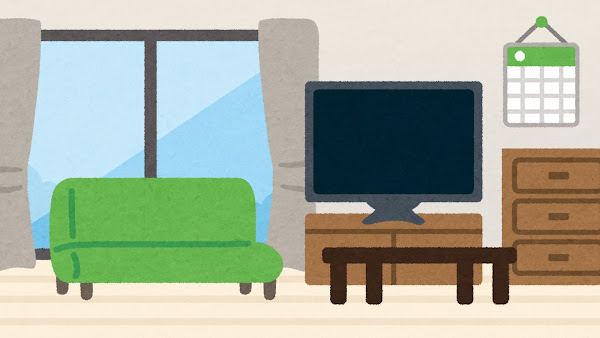
スッキリとした部屋でリラックスしている自分の姿を想像することで、「やっぱり片付けたい」という気持ちをあらためて強くすることができます。
インテリア雑誌の切り抜きや、ネットで見つけた理想の部屋の画像などを見るようにするのもいいですね。
「1日5分」「1か所だけ」から始める

「よし、やるぞ!」と意気込んでも、いきなり家全体を片付けようとすると挫折しがちです。
まずは、洗面所の引き出し1つ、キッチンの棚1段、玄関の靴箱の一部など、ごく小さなスペースから始めてみましょう。
「今日はここだけ」「タイマーで5分だけ」と決めて取り組むと、驚くほど気軽に始められます。
それでもやる気が出ない。。。
というときに使えるテクニックやNG行動をこちらでご紹介しています。
ぜひチェックしてみてください!
↓ ↓ ↓

私が実践してうまくいった「小さな片付け成功体験」
私自身も、実は長年「捨てられないタイプ」でした。
「いつか使うかも」「もったいない」「思い出がある」
そう思って、なかなか手放せなかったんです。
でも、少しずつ片付けを続けたことで、「手放すって気持ちいい」と感じられるようになりました。

ここでは、私が実際にやって効果があった2つの「小さな成功体験」を紹介します。
体験談1:キッチンの「使っていないグッズ」を5分だけ整理
ある日、「とりあえず5分だけ」と思って、普段はあまり開かないキッチンの引き出しを1つ開けてみました。
すると、使っていない調理器具やおまけのタッパーがごそっと出てきたんです。
「これは使ってない」と思えるモノばかりで、ほとんど空っぽになるほど、10点以上手放すことができました。
1つの引き出しを片付けたことで、他の引き出しの物を片付いた引き出しに再収納。
メインで使う引き出しが使いやすくなり、「あ、気持ちいい!」と実感できた初めての瞬間でした。
体験談2:「保留ボックス」が気持ちをラクにしてくれた
次に実践したのが「保留ボックス」。
思い出のある洋服や文房具など、今は使ってないけど捨てづらい…
そんなモノをとりあえず入れておいたんです。
数か月後に見返したとき、「なくても大丈夫だったな」と手放せたものも多数ありました。
「今決めなくていい」というルールが、私にはとても合っていました。
小さな成功が片付け習慣を作る
片付けは、大きく変わる必要なんてありません。
「できた!」と感じられる小さな成功を積み重ねることで、自信と習慣が育ちます。
私の体験が、あなたの最初の一歩のヒントになればうれしいです。
番外編:「手放す」以外の片付け方法も知っておこう
「捨てる」ことばかりが片付けではありません。
整理整頓を工夫
モノをカテゴリー別に分け、使用頻度に合わせて配置するだけでも、収納は格段に使いやすくなります。
整理整頓のコツはこちらにまとめています!
↓ ↓ ↓

スペースの有効活用
突っ張り棒や収納ケースなどを活用して、縦長のスペースを効果的に使う工夫をしましょう。
「増やさない」工夫
新しいモノを買う前に「本当に必要か?」と自問自答する習慣をつけましょう。
そのとき「今、必要かな?」ということを意識してみてください。
「今」というのはとても重要なキーワードなんですよ!
物を増やさないために一番おすすめなのが「1アウト1イン」という方法です。
詳しくはこちらにまとめましたので、ぜひチェックしてみてください!
↓ ↓ ↓


物を減らすことが片付けの大きなポイントです。収納方法や空きスペースの活用には限界があることを覚えておきましょう!
まとめ:少しずつ、あなたのペースで大丈夫!
「捨てられない」という気持ちを抱えながらの片付けは、困難な道かもしれません。
片付け初心者であればなおさらです。
思い出の品なんかは、プロでも悩む難問なんですよ!
今回ご紹介した3つのルールとコツを小さいことから実践していくことで、必ず変化は訪れます。
大切なのは、焦らず、自分のペースで進めること。
今日、何か一つでも保留ボックスに入れたり、手放したりしてみましょう。
その小さな一歩が、きっとあなたの暮らしをより明るく、より快適なものへと導いてくれるはずです。
片付けって記述なんです。
他のことと同じで、すればするほど成長していきます。
残す・手放すの判断もすばやく、正確にできるようになってきます。
無理せずに続けることで、片付けがどんどんはかどるようになってきますからね。
無理せず、楽しくがんばっていきましょう!
不用品を手放す方法はこちらでもまとめています。
ぜひ該当の項目をチェックしてみてください!
↓ ↓ ↓


