「ねぇ、何度言ったら分かるの!?モノを置きっぱなしにしないでって!」
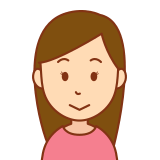
何度言っても改善されないの。。。
…はい、これは数年前まで、私のいつものセリフでした(苦笑)。
仕事から疲れて帰ってきて、散らかった部屋を見るとドッと疲れが増して、つい家族にイライラをぶつけてしまっていました。
あなたも、そんな経験ありませんか?
「家族みんなで片付けて、スッキリした家で過ごしたい」と思っているのに、現実は「私ばっかりがんばってる…」なんて思っていました。
「40代から始める片付け|リバウンドなし&不用品売却ガイド」のりょうこです。
40代、夫と中学生の息子の3人暮らし、賃貸マンションで暮らしています。
仕事と家事の両立で毎日ヘトヘトな中、家族の協力がないのに、理想の「リラックス空間」なんて夢のまた夢…
あきらめかけていた時期もありました。

でも、試行錯誤の末に気づいたんです。
大切なのは、一方的に指示することではなく、家族みんなが「片付けたいな」と思えるような進め方をすること。
そして、ちょっとした声かけのコツなんだって。
かつての私と同じように「家族が片付けに協力してくれない!」と悩む40代のあなたへ。
ストレスゼロで家族みんなが気持ちよく片付けに取り組めるようになるための具体的な進め方とコツを、私の失敗談も交えながらご紹介します。
片付けにおける家族の役割と驚きのメリット
「結局、私がやった方が早いわ…」そう思ってしまう気持ち、すごくよく分かります。
でも、長い目で見ると、家族みんなで片付けに取り組むことには、計り知れないメリットがあるんです。
1. 自分の負担が激減!
当たり前ですが、一人で抱え込むより、家族で分担すれば自分の作業量はぐっと減ります。
時間的にも精神的にも余裕が生まれますよね。
共働きで忙しかったり、家事をこなさいといけなかったり。
そんな中で片付けに取り組むときに、作業量が少ないのはありがたいですよ!

私たちにとって、負担が軽減するということは本当に大きなメリットなんです!
2. 家族の会話が増える!
一緒に作業をすることで、自然と会話が生まれます。
「これ、懐かしいね!」「これはどこに置こうか?」なんて話しながら片付けるのは、意外と楽しい時間になったりします。
家族みんなで一緒に心地よい自宅を作る。
一丸となって何かに取り組む、というのがいいんですよね!
3. モノを大切にする心が育つ!
家族それぞれが自分のモノと向き合うことで、「これは本当に必要かな?」「大切に使おう」という意識が芽生えます。
特に子どもにとっては、モノを整理する習慣を身につける絶好のチャンス。

自分で取り組むからこそ得られる、貴重な経験・成長です。
4. 子どもの成長にもつながる!
片付けを通して、計画性や判断力、そして自分の持ち物に責任を持つという大切なことを学べます。
子どもの頃から物との付き合い方を考えられる経験は大きいですよ。
大人になって、あらためて片付けや物との付き合い方を学ばなくていいようにする。
これは親の大ファインプレーなんです!
5. 達成感を共有できる!
「みんなでがんばってキレイにしたね!」という達成感は、何物にも代えがたい喜び。
家族の絆をより一層深めてくれます。
家族みんなで作り上げた空間なら、キープする気持ちもまったく違います!

家族みんなで片付けに取り組めたら、すばらしいと思いませんか?
毎日が劇的に良くなりそうですよね!
なぜうちの家族は協力してくれないの?よくある原因とそれぞれの心理
「メリットは分かったけど、うちの家族は全然動いてくれないのよ…」という声が聞こえてきそうです。

その背景には、実は様々な原因と心理が隠れているんです。
夫が協力しない心理
まずは夫が協力してくれないケースを見ていきましょう。
- 「片付けは妻の仕事」という古い価値観が残っている(無意識の場合も…)。
- 「どこから手をつけていいか、具体的に何をすればいいか分からない」(慣れていないので具体的な指示がないと動きにくい)。
- 過去に片付けを手伝ったら、やり方をダメ出しされてやる気を失った。
- そもそも、今の状態を「散らかっている」と認識していない(美的感覚の違いも…)。
例えば「片付けに慣れていないからどうしていいか分からない」ということはよくあることです。
初心者向けの記事を読んでもらうことで、動いてもらいやすくなるかもしれません。
↓ ↓ ↓

私も以前、

リビングの床にモノを置かないで!
と毎日キーキー怒っていたら、夫はどんどん協力的じゃなくなってしまいました…。
今思えば、そうなりますよね。。。って感じです。。。
子どもが協力しない心理(年齢別)
次に子どもが協力してくれないケースについて見ていきます。

小学生(低学年~中学年)
- 「片付け=面倒くさいこと」と思っている。
- 遊びの延長で散らかしてしまい、片付けるという概念がまだ薄い。
小学生(高学年)~中学生
- 自分の部屋は自分の好きにしたい!(プライバシーの主張)
- 勉強や部活で忙しいし、時間があるならゲームや趣味の時間にしたい!
- 後でやるって言ってるのに!(反抗期も影響?)
息子が中学生になった今も、教科書や部活の道具がリビングに置きっぱなし…
なんてことは日常茶飯事。
「自分のモノなんだから自分で管理して!」と言っても、なかなか響かないんですよね。
家族共通の心理
そして、私にも言えるみんなに共通する心理状態について解説します。

指示や命令口調への反発
「~しなさい!」「なんで片付けないの!」と強く言われると、誰でもやる気をなくしますよね。
片付けのゴールが見えない不安
「どこまでやれば終わりなの?」と途方に暮れてしまう。
ゴールや締切がないとなかなか動けないものです。
モノに対する価値観の違い
自分にとっては不用品でも、家族にとっては大切な「お宝」かもしれません。
物の量も、人によって基準が違いますよね。
もし、ご家族が片付けに協力的でないとしたら、上記のどれか、あるいは他にどんな理由が考えられますか?
その気持ちに寄り添い、軽減することができそうですか?

自分に置き換えてみると、協力しない気持ちもよく分かります。
でも、つい忘れてしまうことも多いんですよね。。。
【実践編】ストレスゼロで家族に協力してもらう!片付けの進め方7ステップ
「メリットも原因も分かった。じゃあどうすればいいの?」
ここからは、いよいよ具体的な実践編です!
家族みんなが気持ちよく協力してくれるようになるための、魔法のような7つのステップをご紹介します。
ステップ1:まずは自分の「ご機嫌」から!笑顔で「お願い」ムードを作る
これはすべての土台になる部分。
とっても大事なところです。
私自身、イライラしながら「片付けてよ!」「手伝ってよ!」と言っていたときは、まったく効果がありませんでした。
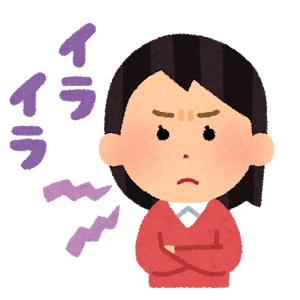
むしろ逆効果…。
そりゃ、イライラをまとった状態で頼まれると、協力したくなくなりますよね。。。
まずは、自分自身が深呼吸してリラックス。
そして、「週末、リビングをスッキリさせたいんだけど、手伝ってくれるとうれしいな」と、笑顔で、お願いする形で伝えてみましょう。
「~してほしいんだけど、どうかな?」と相談するようなトーンも効果的です。
「楽しいことを一緒にしようよ!」という雰囲気を出せれば、協力したくなるかもしれません。
NG例
- 「なんで誰も手伝ってくれないの!」
- 「はあ…結局私ひとりか…(ため息)」
- 無言でイライラしながら片付け始める
無言・ため息・怒りの空気は、周りに「近寄るな」という信号として伝わってしまい、家族はますます距離を取ります。
協力を取り付けるどころではなくなっちゃいます!

これまでにどういうふうにお願いをすると、家族は協力してくれましたか?
そのときのことを思い出してみましょう!
ステップ2:「家族会議」で目的とゴールを共有する(見える化も効果的!)
「なんで片付けなきゃいけないの?」
この疑問に答えることが、協力への第一歩。
家族みんなで集まって、「なぜ片付けが必要なのか」「片付いたらどんないいことがあるのか」を話し合いましょう。
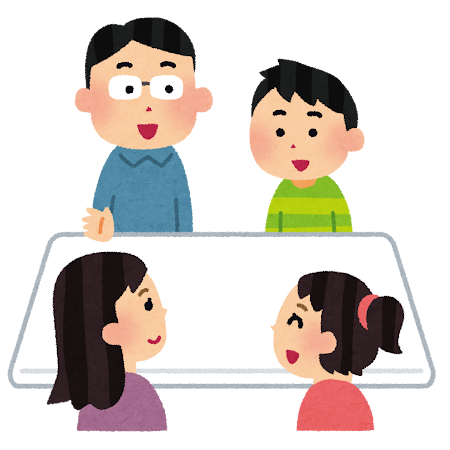
例えば。。。
- 「探し物がすぐに見つかるようになって、朝の準備時間が短くなるよ!」
- 「リビングが広くなって、みんなで映画を見たり、ゲームをしたりできるね!」
- 「お友達を気軽に呼べるようになるよ!」
などなど、具体的なメリットを伝えるのがポイント。
理想の部屋の写真を雑誌やインターネットで見つけてきて、「こんな部屋にしたいね!」と共有するのもいいですね。
「リビングの床には何も置かない」「テーブルの上はいつもスッキリ」 といった簡単な目標を紙に書いて、みんなが見える場所に貼っておくのも効果的です。

家族みんなが快適に過ごせる空間を作っていきたいですね。
そのためには家族での話し合いは不可欠です!
家族会議をスムーズに進めるためのお菓子や飲み物があると、なお良いかもしれませんよ♪
全体的な片付けの目標が決まったら、その日の目標やゴールを決めてみましょう。
片付けの定番である「小さな場所から始める」のがおすすめです。
達成感の積み重ねで、片付けに対するモチベーションが維持・向上しますよ!
NG例
- 「今日中に全部終わらせて!」
- 「とにかくどんどん片付けていくよ」
これらはゴールがあいまいで、気持ちが盛り上がりにくいです。
OK例
- 「今日はこの引き出し1段だけ一緒にやってみない?」
- 「靴箱の片付けを徹底してやってみよう!」
まずは小さな範囲から始めましょう。
片付けに慣れてきたら、だんだん広い範囲も対応できるようになってきますよ!
ステップ3:役割分担は「場所」と「得意」を活かす!押し付けないのが鉄則
「全部自分がやる」のではなく、家族それぞれの役割を決めましょう。
場所で分担
親はリビングの床と自分の部屋、長男は自分の部屋のおもちゃコーナー、長女は洗面所のタオル整理、など。
よく使う場所を担当してもらうと、勝手がわかっているのでスムーズに進みますよ♪
得意なことで分担
男性は重いものを運ぶ、長男はゲーム感覚で細かいものを集める、長女はキレイにたたむ、など。
大切なのは、一方的に役割を押し付けないこと。
「どこならできそう?」「何を手伝ってくれる?」と、本人たちの意思を尊重しながら決めると、責任感が芽生えやすくなります。
責任感を持って取り組むことは、子どもたちの成長にもいい影響を与えます!
みんな得意不得意があります。
適材適所は仕事だけじゃなくて、家庭内でも同じなんです!

普段から家族をしっかり観察して、得意なことを見極めておくといいですね。
ステップ4:「捨てる」のプレッシャーを減らす!「要る・要らない・迷う」の3分類BOX作戦
「捨てなさい!」

この言葉は、家族の心を閉ざしてしまいます。
誰しも強要されるのは嫌なんです。
特にモノへの愛着が強い家族がいる場合はそうですね。
こんな場合は、「捨てる」のではなく「残したいモノを選ぶ」という意識に切り替えてもらうのがコツ。
「要るモノ」「要らないモノ」「迷うモノ(一時保管)」の3つの箱を用意し、各自で分類してもらいましょう。
このとき、「要らないモノ」の箱を「ありがとうの箱」と名付けるのもおすすめです。
感謝の気持ちを込めて手放す、という意識が芽生えます。
「迷う箱」に入れたモノは、「1か月後にもう一度見直そうね」と明確に期限を決めておくことも忘れずに。
共有のカレンダーなんかに、書き込んでおくのも大事です!

NG例
- 「これもう使ってないでしょ?捨てなよ」など即断を求める
- 「なんでまだこんなもの取ってあるの?」と責める
- 「捨てないならやらなくていい」など極端なルール設定
捨てることを強要すると、相手の気持ちが防御モードになります。
自分の価値観を否定されたような気持ちにもなります。
協力どころか反発される可能性がぐっと高まって、逆効果間違いなしです!
声かけ例
- 「これは迷う箱に入れて、またあとでゆっくり考えようか」
- 「捨てるかは置いといて、まず使ってるかどうかだけ見てみよう」
- 「迷ったらとりあえず保留!大事なものだったら残せばいいよ」
判断を保留できる余白を与えることで、家族も安心して片付けに参加できます。
このステップは特に「片付けに苦手意識がある家族」に有効で、「やらされている」感を軽減し、自主的な判断につながりやすくなります。
捨てる・手放すことのつらさ・苦労を味わえば、買うときに考えるようになります。
いい空間をキープするためにも、一人ひとりが判断することが大事です!
ステップ5:子どもも楽しく参加!「ゲーム感覚」と「できた!」の褒め言葉シャワー
特に小さなお子さんには、「片付け=楽しいこと」というイメージを持たせることが大切です。
ゲーム感覚
「よーいドン!で、おもちゃを箱に入れよう!」「どっちがたくさん集められるかな?」とタイマーで競争する。
お気に入りの音楽をかけながらノリノリで片付ける。
など、ちょっとした工夫で、嫌だと思っていたことが楽しいものになります。
ご褒美シール
がんばった場所にシールを貼ったり、スタンプカードを作ったりするのも効果的。
小学生以下の子どもにめちゃくちゃ効きますよ!
褒め言葉のシャワー
これが一番重要!
「わぁ、キレイになったね!ありがとう!」
「〇〇ちゃんが手伝ってくれたから、すっごく助かったよ!」
具体的に、大げさなくらいに褒めましょう。
「できた!」という達成感が、次へのやる気につながります。
大きくなっても同じです。
どんどん褒めて褒めて、やる気を出してもらいましょう!

お子さんや家族が一番喜びそうな「お片付けゲーム」や「ご褒美」は何だと思いますか?
ステップ6:途中でケンカ勃発?「まあ、いっか」と「仕組み」の見直しで乗り切る
家族で片付けをしていると、途中で意見がぶつかったり、思うように進まなくてイライラしたり…
そんなこともありますよね。
私も夫と「これはまだ使える!」「いや、もういらないでしょ!」と何度言い合ったことか…。

つい感情的になってしまうこともあります。
でも、ぶつかり合わないことが大事!
まずは深呼吸。
「今日はここまでにして、また明日考えようか」と区切るのも一つの手です。
その日にその場所を片付けるのは終わりにして、別の場所に取りかかるのもいい方法ですね。
また、何度も同じことで揉めている場合、「人のせい」ではなく仕組みやルールそのものを見直すチャンスかもしれません。
NG例
- 「だから言ったでしょ!」と過去のことを責める
- 「もういい!一人でやる!」と片付けを打ち切る
- 「あなたはいつもこう」など人格批判につなげる
一度ヒートアップすると、片付けどころではなくなり、信頼関係にも悪影響。
その後の家族の時間も嫌なものになってしまいます。
過激なことを言いたくなっても、ぐっと我慢です!
声かけ例
- 「ちょっと一回休憩しようか!お茶でも飲も〜」
- 「うまくいかないのはやり方かも。やり方変えてみよっか」
- 「ここはまた次回にして、あっちをしてみようか」
落ち着いて仕切り直しを提案し、対立より改善に意識を向けましょう。

片付けは「完璧にやること」より「家族の関係を壊さないこと」の方がずっと大事です。
「完璧」を目指しすぎず、「まあ、いっか。少しでも進んだからOK!」と考えることが、ストレスを溜めないコツです。
そもそも片付けに「完璧」はありません。
ゆっくりとやっていきましょう!
ステップ7:片付け後は「ありがとうパーティー」!快適さを共有し、感謝を伝える
片付けが終わったら、がんばった家族みんなで、キレイになった空間を思いっきり楽しみましょう!

好きなお菓子やジュースを用意して、「お疲れ様パーティー」を開いたり、スッキリしたリビングでみんなで映画を見たり。
「みんなでがんばったから、こんなに気持ちいいね!」 と、快適さを共有することが大切です。
そして、改めて「手伝ってくれて本当にありがとう。すごく助かったよ」と、一人ひとりに感謝の気持ちを伝えましょう。
この「良い記憶」が、次回の片付けへの協力につながっていくはずです。
家族はどんな食事を作れば喜んでくれますか?
前もって食材の準備をしておくといいですね。

片付けを始める前に、「今日の夕食は○○だよ!」と公開しておくのもいいですね!
【相手別】夫・子どもに響く!片付け協力の魔法の言葉とアプローチ法
さらに、家族のタイプに合わせたアプローチで、よりスムーズな協力を引き出しましょう。
配偶者に協力してもらうコツ
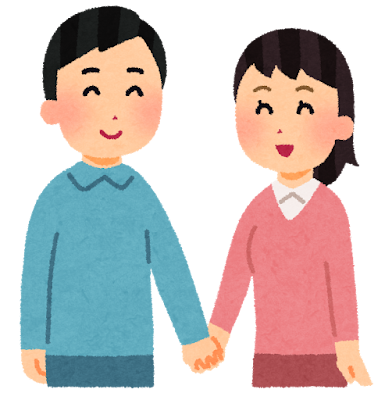
まずは夫や妻、配偶者に協力してもらう方法です。
「困っているから助けてほしい」と素直に頼る
「私一人じゃ大変で…あなたの力が必要なの」と、頼りにしている気持ちを伝えましょう。
誰でも「頼られる」と力を発揮しやすいものです。
具体的に「何をしてほしいか」を伝える
「リビングの雑誌をまとめてほしい」「この棚のモノを全部出して、要るモノと要らないモノに分けてほしい」など、具体的な作業内容を伝えましょう。
漠然としたお願いだと、頼まれた方も動きにくいんですよね。
片付けのメリットを夫目線で伝える
「探し物がすぐに見つかるようになるから、朝の準備が楽になるよ」「趣味の道具を置くスペースができるかもね」など、相手のメリットを提示すると効果的です。
お互いのスペースやモノには口出ししすぎない
お互いの持ち物や書斎など、個人の領域については、本人の意思を尊重しましょう。
「これはどうする?」と相談する形が良いですね。
感謝の言葉は具体的に、そして効果的に
「重いもの運んでくれてありがとう!すごく助かった!」「おかげでスッキリしたよ、さすがだね!」など、具体的に褒めるとモチベーションもアップします。
お互いにメリットになるポイントを伝えられると最高ですね!
子どもに協力してもらうコツ(年齢別)

次に、子どもに協力してもらう方法です。
小学生(低学年~中学年)
遊びの延長で楽しく!
「おもちゃのおうちを作ってあげよう!」「どっちがたくさんお片付けできるか競争だ!」など、遊びの要素をふんだんに取り入れましょう。
分かりやすい言葉で、短時間で!
「この赤い箱にお人形さんを入れてね」「5分だけがんばろう!」など、具体的で短い指示が効果的です。
お手本を見せる
親が楽しそうに片付けている姿を見せるのが一番の教育です。
小学生(高学年)~中学生
「なぜ?」をきちんと説明する
「部屋が片付いていると勉強に集中できるよ」「お友達を呼びやすくなるよ」など、片付けのメリット・理由を具体的に説明し、納得感を持たせることが大切です。
自分のモノは自分で管理する責任感
「自分の部屋のモノは、自分で責任を持って管理しようね」と伝え、自主性を尊重しましょう。
計画やルール作りに参加させる
「いつ、どこを片付けるか」「どんな風に収納するか」など、子ども自身の意見も取り入れながら一緒に計画を立てると、主体的に取り組みやすくなります。
プライバシーの尊重
勝手にモノを捨てたり、部屋をチェックしたりするのはNG。
信頼関係を大切に。
ご褒美の工夫
モノだけでなく、「ゲーム時間が少し増える」「好きなことにかける時間が増える」といった、子どもにとって魅力的なご褒美も効果的です。

子どもにとってご褒美は、ものすごい効果があります。
中毒にならないように上手に使いたいですね。
よくある質問FAQ
よくある質問をまとめてみました。
Q1: 子どもが片付けを全然やってくれません。どうすればいいですか?
子どもは「片付け=面倒でつまらないこと」と感じがち。
ゲーム感覚にしたり、「ぬいぐるみをおうちに帰す」など、わかりやすい目的と遊び要素を取り入れると、自発的に動いてくれることが多くなります。
完璧を求めすぎず、小さな成功体験を積ませましょう。
Q2: 夫(または妻)がまったく協力的じゃなくてイライラします…
大人も「やらされ感」があると動きにくいもの。
まずは強制せず、「一緒にしてくれると助かるな」などお願いベースでの声かけがおすすめです。
相手が乗ってこない場合は、「じゃあ〇〇だけお願いしてもいい?」と小さな役割から任せてみましょう。
Q3: 「捨てたくない!」と反発されます。どうしたらいいですか?
片付けの初期段階では、「捨てる」より「分ける」ことを優先しましょう。
「要る・要らない・迷う」の3分類を提案し、判断を保留できる仕組みにすることで、心理的なハードルが下がり、話し合いがスムーズになります。
Q4: 一緒に片付けていたのに途中でケンカになってしまいます…
片付け中のケンカはよくあること。
ヒートアップしそうになったら、いったん休憩して仕切り直す勇気も大切です。
問題が何度も起こるようなら、感情ではなく「仕組み」や「進め方」に原因がないか見直してみましょう。
Q5: 家族が片付けたあと、すぐに元通りに散らかってしまいます。
リバウンドは、「元に戻す場所=定位置」が決まっていないことが原因です。
物の定位置を一緒に決めたり、「1日5分のリセットタイム」など、小さな習慣づけで維持しやすくなります。
まとめ:イライラを手放し、家族みんなで笑顔になる片付けを
家族で片付けに取り組むと、単に家がきれいになるだけではありません。
家族のコミュニケーションを豊かにし、お互いをより深く理解し合うことにつながります。
大切なのは、完璧を目指さないこと、焦らないこと。
そして何よりも、家族みんなが気持ちよく協力できる方法を見つけること。
「私ばっかり…」というイライラを手放し、家族みんなで笑顔になれる片付けを、今日から少しずつ始めてみませんか?
まずは、ステップ1でお伝えしたように、自分自身の「ご機嫌」を整えることから。
そして、家族に笑顔で「ちょっと手伝ってほしいな」と、小さな「お願い」から伝えてみてください。
きっと、あなたの想像以上に、家族は力を貸してくれるはずですよ。
楽しみですね!
せっかく片付いた家をキープするには収納方法も大事です。
収納のコツをまとめたので、ぜひチェックしてみてください!
↓ ↓ ↓



